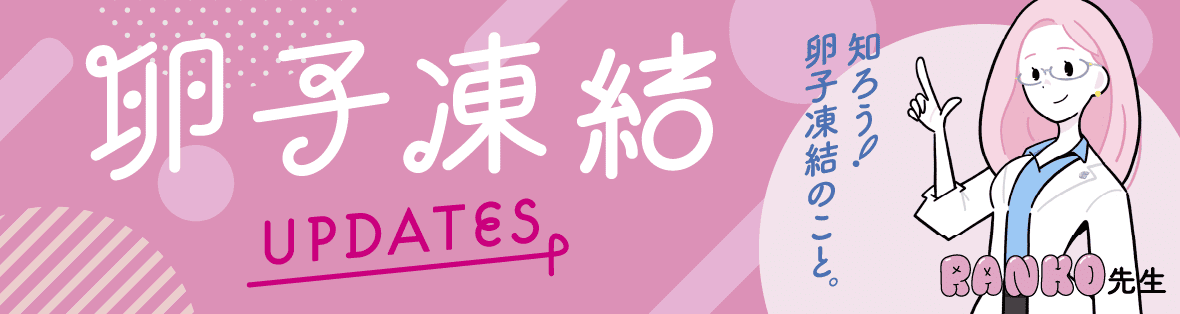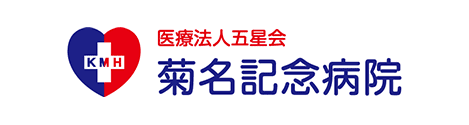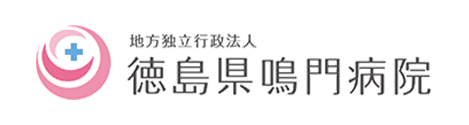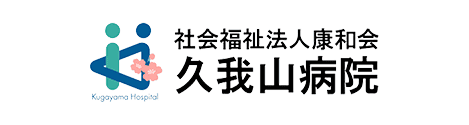卵管造影(HSG)で「とても痛かった」と感じたとしても、その痛みが何を意味するかは人によって異なります。検査時の刺激や緊張で起こるけいれん(攣縮)に伴う一時的な痛みの場合もあれば、造影剤が実際に通らない状況に関連する痛みの場合もあります。両者の区別は、その後の検査や治療の選択に直結します。本記事では「痛みの背景の見分け方」「画像を見るときの要点」「次のステップ」をまとめます。
HSGで起こりうる痛みの種類
HSG時の痛みは主に次の三つに分けて考えると整理しやすくなります。
- ① けいれん(攣縮)に伴う痛み:検査中の緊張、頸管・子宮の刺激、造影剤を入れるスピードなどに反応して一時的に収縮が強く出ることがあります。痛みと同時に「通りが悪いように見える」ことがあり、再評価で所見が変わることもあります。
- ② 実際の通過障害に伴う痛み:近位(卵管の入口部分)・遠位(卵管の末端部分)いずれかの狭窄/閉塞、癒着、卵管水腫の示唆などが背景にあると、造影剤が先へ進まず停滞し、圧がかかって痛みとして感じることがあります。
- ③ その他:カテーテル挿入時の違和感、頸管の形や検査時の姿勢に伴う張り、心理的な緊張など複合要因。
けいれん(攣縮)とは?
けいれんは、子宮・卵管の筋肉の反射的な動きが一時的に強く出た状態を指し、画像上は近位(卵管の入口部分)で造影剤が細く途絶えるように見えることがあります。検査の進め方や呼吸、体位、造影剤の条件などで差が出るため、所見がずっと詰まっている状態を意味しない場合があります。検査中にできる工夫として、深呼吸や声かけ、痛みや違和感の早めの訴えなどが挙げられます。鎮痙薬・鎮痛薬などの使用可否は医師の判断に従いましょう。

「通らない痛み」を疑うサイン
実際の通過障害が疑われるのは、次のような状況が複数重なっているときです。
- ・造影剤が卵管の先端で停滞し、腹腔内への広がり(もやっとした拡散像)が乏しい。
- ・遠位側(卵管の出口部分)の膨らみ(卵管水腫を疑う所見)や、左右差の大きい停滞像がある。
- ・過去のクラミジア感染や腹部手術、内膜症など、通過障害の背景となりうる既往がある。
- ・検査時の痛みが強く、終了後もしばらく違和感が残るなど、症状が画像所見と合致している。
ただし、「痛かった=閉塞」と単純に結びつけることはできません。医師から説明を受け、わからない点は遠慮なく質問しましょう。
画像の見方
HSGは位置と程度を整理するのがコツです。次の4つの「フレーム」で見ると、医師との対話がスムーズになります。
- 開始像:子宮腔の形、造影剤の入り方。頸管の通過で過度の抵抗がないか。
- 中間像(卵管近位~中部):左右差、ビーズ状や糸状に狭くなっている、途絶の位置。
- 末端像(卵管の出口部分):ふくらみ(袋状)や狭さ。水腫を疑う所見の有無。
- 拡散の様子:腹腔内への広がりが十分か、片側のみか、時間経過で変化があるか。
自己判断は難しいため、可能であれば画像を見ながら説明を受けましょう。画像がもらえる場合は、結果票と一緒に保管しておくと、その後の相談がスムーズです。

よくある例
A:けいれん(攣縮)疑いが強い
近位(卵管の入口部分)で細く見えるが、時間経過や軽い体位調整で抜けが確認できた/痛みはピーク後に速やかに軽快──といった場合。
短期の計画的な様子見(漫然と続けない)+必要なら再検査へ。
体調・睡眠・冷え対策・緊張緩和など、当日の条件を整えるだけで所見が変わることもあります。
B:近位(卵管の入口部分)の構造的な詰まりが疑われる
近位で途絶し、拡散が乏しい/左右差が大きい/既往と整合──などの場合。
卵管造影で再評価し、状況に応じてFTを含めた評価を検討します。適応が見込まれる場合に限り、目的・限界・代替案・リスク・術後計画を共有して合うタイミングでFT(卵管鏡下卵管形成術)を検討します。
C:遠位(卵管の末端、出口部分)の癒着・卵管水腫が疑われる
先端で袋状にたまり、広がりが乏しい/卵管の先端で、繰り返し同じように見える所見─などの場合。
腹腔鏡での評価・処置やIVF前処置の検討が優先されることがあります。年齢・他因子・時間軸を加味して、IVFを含む診療計画立てます。
医師に伝えるとよい「痛みの項目」
- ・痛みのタイミング:注入直後/途中/終了後など。
- ・場所と性状:痛みに左右差はあるか、差し込む/重い/張る等の表現。
- ・持続時間:ピークの長さ、軽快までの時間。
- ・随伴症状:吐き気・冷汗・ふらつき・発熱など。
- ・過去との比較:前回HSGや他検査と比べてどうか。
これらは、けいれんか通過障害かを推測するうえで役立ちます。
検査の負担を減らすコツ
- ・体調と時間帯:無理のない日時に予約。睡眠・食事・水分を整えましょう。
- ・防寒とリラックス:検査室は肌寒いこともあります。靴下や羽織り、深い呼吸を意識しましょう。
- ・痛みを伝えるタイミング:痛みは我慢せず早めに伝えましょう。進め方の調整につながることがあります。
- ・薬の可否:鎮痙薬・鎮痛薬等の可否は医師の判断に従いましょう(自己判断での服用は避ける)。
- ・同意と説明:検査の目的・限界・一般に起こり得るリスクを事前に確認しましょう。

次のステップ
- 再評価:画像と結果票のセット確認。必要に応じて部分的な卵管造影で近位を精査。
- 選択:①計画的な様子見/②FTの検討/③腹腔鏡・IVF前処置/④IVFの準備を、価値観×時間軸×医学的所見の交点で決定。
- 見直し:数周期(目安3か月)で振り返り、結果に応じて軌道修正。
※記載した検査・手技の実施可否、保険適用や運用は施設によって異なります。詳細は受診先でご確認ください。
ケースごとの違い
自然妊娠を希望される方は、再評価で通過性の改善が期待できるときに、タイミング法や人工授精(AIH)を数周期(目安3か月)実施します。一方、体外受精を検討されている方は、年齢や他因子、仕事のスケジュールなどを踏まえ、IVFの準備・前処置を先に進める選択が適することがあります。
検査後3か月で見直す
痛みの背景に応じて方針を決めたら、数周期(目安3か月)で振り返るポイントを合意しておくと、「漫然とした様子見」を避けられます。結果が得られない場合は次のステップを、良い変化があれば現在の方針のどこを強化するかを一緒に検討します。妊活の記録(実施内容・体調・感想・相談事項)を簡単に残しておくと、面談が効率的になります。
よくある誤解
- ・「痛かった=閉塞に違いない」:けいれんでも強い痛みが起こり得ます。画像と症状を合わせた判断が必要です。
- ・「様子見=何もしない」:計画的な様子見は、期間・評価指標・見直し時点を決めた能動的なプロセスです。
- ・「画像は見せてもらえないもの」:施設により保管状況は異なりますが、結果票と一緒に画像を確認する姿勢が大切です。発行方法や形式を窓口に相談しましょう。
- ・「FT(卵管鏡下卵管形成術)は必ず必要/必ず不要」:適応は一人ひとり違います。近位の通過不良が疑われる場合に、合う人に、合うタイミングで検討されます。

助産師より

検査による痛みは、とてもお辛く、妊活を続けられるのか不安になりますよね。また痛みがあると、「実際に通りにくさがあるのかもしれない」と考えるのも自然な気持ちです。
もし近位で通過不良が疑われる場合には、FTという方法で卵管の通りを改善できる可能性があります。すべての方に必要ではありませんが、合う状況で行えば自然妊娠やAIHのチャンスを広げられることもあります。大切なのは「自分にはどんな選択肢があるか」を医師や助産師と一緒に整理していくことです。痛みや不安を抱え込まず、安心して次の一歩を進められるよう、私たちが寄り添っていきます。